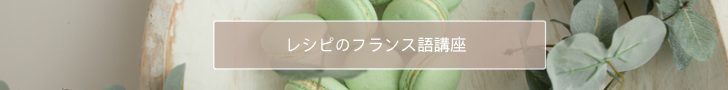フランスの宗教的な祝日である11月1日の諸聖人の日(トゥサン Toussaint)について解説と、お菓子との関係について紹介します。
諸聖人の日とは?
諸聖人の日はフランスではトゥサン(Toussaint)といい、その名の通り「全ての(tous)聖人(Saint)」を祝うカトリックの祝日のことです。起源は古く、中世時代の12世紀に制定されました。カトリック教会では11月1日が諸聖人の日で、翌日の11月2日が死者の日(Jour des Morts)となっています。
フランスの学校ではこの諸聖人の祝日の前後の2週間が毎年バカンス(秋休み)となっています。11月2日にはお墓参りに行くのが習慣です。日本の8月のお盆のような感じですね。
諸聖人の日のお菓子
フランスやヨーロッパ各地で諸聖人の日に食べるお菓子があります。
パヌレ Pannelets
南フランスのピレネー=オリアンタル県のルシヨン (Roussillon)地方ではパヌレというお菓子が作られています。パヌレ(pannelets)とはアーモンドで作った生地を松の実でまぶした小さなお菓子です。この地方では『パヌレのない諸聖人の日ははヌガーのないクリスマスと同じくらい寂しい』という諺があるくらいです。
スペインのカタルーニャ地方では900,000kgものパヌレが諸聖人の日のために準備された年もあるんだそうです。
900 000 kg de “panellets” catalans pour la Toussaint, la rousquille risque d’en pâlir de jalousie !
二フレット Niflette
また、パリ近くのセーヌ=エ=マルヌ県にあるプロヴァンでは、諸聖人の日に伝統的に二フレットというお菓子が食べられています。
プロヴァン(Provins)とは中世時代に栄えた都市で、その名残の残る街並みはユネスコの世界遺産に登録されています。
二フレット Nifletteとはクレーム・パティシエールを詰めた折り込みパイ生地のタルトレットで、オレンジの花の水で香り付けすることもあります。いわゆる、エッグタルトのことです。
二フレットは中世時代から食べられていて、もともとは親を亡くした孤児のために作られていました。二フレットという名前は Ne flete(ヌ フレット「もう泣かないで」)という表現に由来しています。その言葉から Renfler (膨れる)という動詞が使われるようになりました。
19世紀、菓子職人の見習いが二フレットを売るためにプロヴァンの町で移動販売をしていました。
他の地方の伝統菓子
ポルトガルでは『聖人のお菓子 broas dos santos』と言う小さなお菓子が伝統的に作られています。
イタリアのサルデーニャ(Sardaigne)は諸聖人の日と死者の日のために papassinas という小麦粉、豚の脂身、干しぶどう、アーモンド、砕いたくるみで作ったお菓子が作られています。現在では、アイシングを表面に塗っています。
以上、諸聖人の日とその日に食べるお菓子の紹介でした。
おいしい知識を手に入れよう!お菓子のレシピから学ぶフランス語講座
フランスのお菓子は世界的に有名ですが、なぜそのおいしさに魅了されるのでしょうか?
「お菓子のレシピから学ぶフランス語講座」では、フランスのお菓子作りの秘訣を探りながら、同時にフランス語を学んでいきます。
この講座では本場フランスのお菓子のレシピをフランス語で読み解きながら、フランス語を習得します。マドレーヌ、タルト、シュークリームなど、フランスでも定番のお菓子のレシピを通じて、フランス語の基礎から応用まで幅広く学ぶことができます。
フランス語の勉強が初めてでも大丈夫です!当講座では基本的なフランス語表現から、食材や道具の名前、作り方までを丁寧に解説しています。おいしいお菓子のレシピを作りながら、楽しくフランス語をマスターすることができます。
フランス語を学ぶだけでなく、お菓子作りの知識も身につけることができるこの講座は、フランス語学習者とスイーツ好きな方にとって理想的な組み合わせだと思います。ご自宅で学べるダウンロード形式なので、時間や場所に制約されずに勉強することができます。
「お菓子のレシピから学ぶフランス語講座」に参加して、おいしい知識を手に入れましょう!フランス語の魅力とフランスのお菓子作りの楽しさを同時に体験し、自分自身を豊かにしませんか?ご参加をお待ちしています!
関連記事








![サン=ニコラの祝日[12月6日]](https://www.patissieres.com/wp-content/uploads/2020/09/表紙画像_アルファベ-1-1-315x220.png)

![復活祭 Pâques[移動祝日]](https://www.patissieres.com/wp-content/uploads/2023/05/paques-315x220.png)