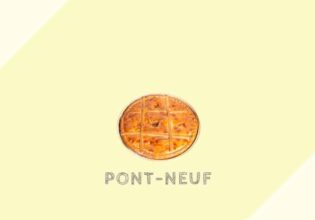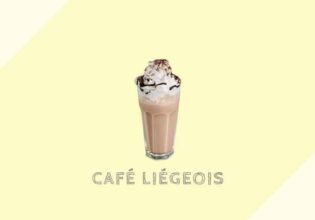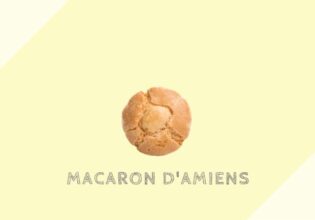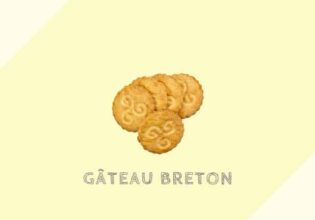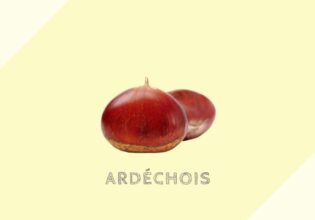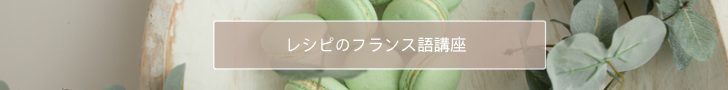フランス菓子アニョーパスカルとはどんなお菓子か、名前の由来や別名、材料を詳しく紹介しますね。
フランス菓子アニョーパスカルとは?
アニョーパスカル Agneau Pascalは仔羊の形をしたお菓子で、フランスのアルザス地方で復活祭のときに食べます。アルザスはグラン・テスト地域圏にあるドイツとスイスに接するフランス東部に位置する地域のことです。
アニョーパスカルは10-20cm程度の高さの小さな雄羊の形をしていて、表面はこんがりと黄金色に焼けていています。ふわふわとした軽い食感の生地です。
ビスキュイ生地を仔羊の形の型に入れ、中火で焼成します。焼成後は型から出し冷まし、粉砂糖を振りかけます。仔羊の首にリボンを結び、黄と白の復活祭(バチカン)、または赤と白のアルザスの小旗を仔羊の肩に飾ります。
復活祭とはフランス語でPâques パックといい、キリスト教でのもっとも重要な祝日で、十字架にかけられて亡くなったキリストが3日後に復活した日のことです。復活祭は春分後の最初の満月の次の日曜日で、毎年日程が異なる移動祝祭日です。だいたい4月のいづれかの日曜日となります。
伝統的には復活祭に日曜日に朝食やおやつとして、カフェやショコラ、紅茶、アルザスの白ワインとともに食べます。
アルデッシュ県(Ardèche)アノネー(Annonay)では、復活祭直前の木曜日である聖木曜日 (le Jeudi saint)にメレンゲでつくった仔羊の形のビスキュイを作っていました。祭壇の上にのせ、町を通り抜ける行進の後に食べていたそうです。
ドイツでは、同じく仔羊の形の Osterlamm を作っていました。アルザスのアニョーパスカルと同じですが、粉砂糖をふりかける代わりにチョコレートでコーティングしています。
アニョーパスカルの別名
名前の呼びかたは地方によって様々で、アニョーパスカルという名前のほかに Osterlammele / Oschterlammele(オステルラマラ)、Lamele / Lammele(ラマラ)とも呼ばれています。コルマールのあるオー=ラン県(Haut-Rhin)では「復活祭の仔羊」という意味があります。
- Agneau Pascal アニョー パスカル
- Osterlammele / Oschterlammele オステルラマラ
- Lamele / Lammele ラマラ
[フランス語名]
アニョーパスカル Agneau Pascal / un agneau pascal
アニョーパスカルの材料
| 分類 | ガトー |
| 構成 |
|
| 材料 |
|
アニョーパスカルの歴史
アルザスでは復活祭の時に仔羊を領主に送るのが慣習となっていました。その習慣はフランス革命まで続き、その後は19世紀末までは子羊を復活祭の日曜日に食べるのが伝統になりました。
その後、仔羊は少しずつ動物型のオステルラマラ Oschterlammele というお菓子に置き換えられていきました。
そのお菓子は仔羊の形に型抜きされたビスキュイで、表面に粉砂糖をふり、リキュール風味の卵と黄と白のバチカン色の小さな旗を飾ります。アルザスでは今もこの伝統が残っています。
仔羊は、磔刑の時と復活祭の日に生き返ったキリストに捧げられた復活祭のシンボルです。
また、その昔、復活祭前の四旬節には卵や肉を食べることが厳しく禁じられていました。40日の四旬節の間にも当然にわとりは卵を産み続け、四旬節が終わるとその卵を消費しなければいけません。四旬節が終わると、家庭の主婦やパン屋は大量の卵を使い、アニョーパスカルなどのごちそうを作っていました。
アニョーパスカルの型
仔羊の型はバ=ラン県 Bas-Rhinのスフレンアイム村 Soufflenhiemの赤土を使って作る陶器が有名です。生地を焼いた後に繊細なお菓子の香りが長く残るのが特徴です。
昔から使われていたアニョーパスカルの型は、ゲルトヴィレ村 Gertwillerのパンデピス博物館に展示されています。
Musée du pain d’épices et de l’art populaire alsacien パンデピスとアルザス民族アートの博物館
アニョーパスカルの歴史は古く、16世紀にはすでに食べられていました。1519年、神学者のトーマス・マナー Thomas Murner の手紙に、男性が婚約者にアニョーパスカルを贈ったとの記述が残っています。この時のアニョーパスカルはお菓子だったのか、仔羊肉だったのかは分かりません。
アニョーパスカルの購入先
アニョーパスカルはブーランジュリーやパティスリーで、復活祭前に購入することができます。復活祭は年によって異なりますが、3月〜4月くらいの時期です。価格はひとつ12-15€ほどです。
おいしい知識を手に入れよう!お菓子のレシピから学ぶフランス語講座
フランスのお菓子は世界的に有名ですが、なぜそのおいしさに魅了されるのでしょうか?
「お菓子のレシピから学ぶフランス語講座」では、フランスのお菓子作りの秘訣を探りながら、同時にフランス語を学ぶ貴重な機会を提供しています。
この講座では、本場フランスのお菓子のレシピをフランス語で読み解きながら、フランス語を習得します。マドレーヌ、タルト、シュークリームなど、フランスでも定番のお菓子のレシピを通じて、フランス語の基礎から応用まで幅広く学ぶことができます。
フランス語の勉強が初めてでも大丈夫!当講座では基本的なフランス語表現から、食材や道具の名前、作り方までを丁寧に解説しています。おいしいお菓子のレシピを作りながら、楽しくフランス語を学ぶことができるでしょう。
フランス語を学ぶだけでなく、お菓子作りの知識も身につけることができるこの講座は、フランス語学習者とスイーツの愛好者にとって理想的な組み合わせです。ご自宅で学べるダウンロード形式なので、時間や場所に制約されずに学ぶことができます。
「お菓子のレシピから学ぶフランス語講座」に参加して、おいしい知識を手に入れましょう!フランス語の魅力とフランスのお菓子作りの楽しさを同時に体験し、自分自身を豊かにしませんか?ご参加をお待ちしています!
関連記事


![復活祭 Pâques[移動祝日]](https://www.patissieres.com/wp-content/uploads/2023/05/paques-120x120.png)