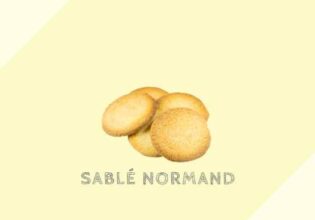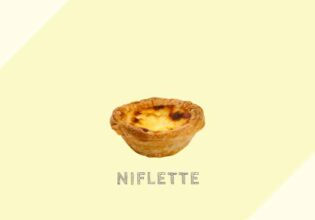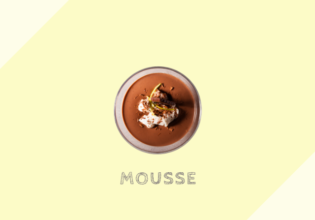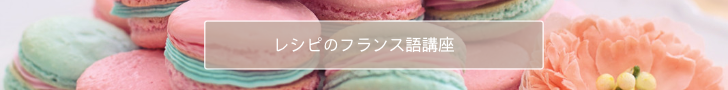フランス菓子パンデピスとはどんなお菓子か、材料や購入先、名前の由来や歴史を詳しく紹介しますね。
フランス菓子パンデピスとは?
パンデピス Pain d’épicesはスパイスと蜂蜜を加えて焼いたお菓子です。スパイスはシナモン、生姜、クローブ、ナツメグやアニスを用いるのが一般的です。
形はパウンドケーキのようですが、バターなどの油脂をくわえないため、やや硬くしっとりとした生地です。そのままスライスして食べますが、薄く切ったパンデピスに好きなチーズをのせて食べると絶品です。特に青カビ系のチーズがよく合います。
ディジョンにあるパンデピスが有名で、昔からパンデピス作りが盛んでした。
クッキータイプのパンデピス
パンデピスにはクッキーのタイプもあります。クッキータイプのパンデピスは、アルザス地方などのドイツや東ヨーロッパでよく見られ、クリスマス時期になるとマルシェなどにたくさんのパンデピスが並びます。
ディジョン(Dijon)はフランスの中央に位置する町で、かつてはブルゴーニュ公国の首都でした。現在ではブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏(Bourgogne-Franche-Comté)の首府です。
ブルゴーニュ公であったフィリップ3世によりディジョンの町にパンデピスが広まっていき、フランス中に知られるようになったのはフランス革命後でした。
[フランス語名]
パンデピス Pain d’épices
フランス菓子パンデピスの材料
| 分類 | パティスリー |
| 材料 |
|
パンデピスに関連するお菓子
アルザス地方でクリスマス時期に食べる地方菓子たちです。
パンデピスのフランスでの購入先
パンデピスはブーランジュリーやパティスリーで購入することができます。ディジョンやアルザス地方ではよく見られますが、一般的な店では必ず置いているわけではありません。クリスマス時期になると、マルシェで売られています。
フランス菓子パンデピスの名前の由来
パンデピスの起源はスパイスを加えていない蜂蜜のパンです。その蜂蜜のパンの起源は2つの説があります。中国で生まれた説ともともとヨーロッパでつくられた説です。
中国で誕生した説
パンデピスの元になった蜂蜜のパンの起源は中国と言われています。10世紀頃、ミ・コン(mi-kong)と呼ばれた蜂蜜入りのパンが食べられていました。ミ・コンとは「蜂蜜のパン」という意味で、小麦粉に蜂蜜を加えて練り、窯で焼いたパンでした。
当時中国ではライ麦が採れなかったこともあり小麦粉をつかい、ハーブで香り付けをしており、お菓子としてではなく食事の一部として食べられていました。
13世紀に入ると、モンゴルのチンギスハンの騎士軍が中国遠征の際に、ミ・コンのレシピを奪いました。
モンゴル騎士軍はすぐにエネルギーになるこのパンを好み、オスマン帝国やヨーロッパへの移動の際に持って行きました。アラブ人も同様にこのお菓子に魅了され、アラブで採れる香辛料を加え、この蜂蜜パンを豊かな味わいにしました。
アラブでは豊富に採れていたスパイスをこのパンに加え、さらに味わい深いものにしました。
そして、十字軍の遠征の際、騎士軍はアラブから香辛料のパンのレシピをヨーロッパに持ち帰りました。
中国で作られていたパンは小麦粉を使用していましたが、東ヨーロッパに伝わる際にその地方で主に生産されていたライ麦を使うようになっていきました。
ヨーロッパでもともと作られてた説
もうひとつの説は蜂蜜パンがヨーロッパでもともと作られていた説です。
蜂蜜パンがヨーロッパでも古い時代からつくられていました。小麦粉などの粉類と甘さをつける蜂蜜があれば、蜂蜜パンを作ることはごく自然なことでした。
フランスでは、修道士によって蜂蜜パンは作られはじめたと言われています。
修道院では蜂蜜がつくられていました。蜂蜜をとるためにミツバチを飼っていて、ミツバチは巣を作るさいに分泌するのが蜜蝋であり、蜜蝋はロウソクの材料となっていました。祈りをささげる際にはロウソクは必要なものなので、修道院で作っていました。
その蜜蝋をつくるための副産物が蜂蜜です。
さらに、修道士は各地をめぐり、信仰を伝える使命をもっていました。彼らは砂糖パン(pains sucrés)や蜂蜜菓子(gâteaux au miel)を作り、巡礼地にて巡礼者に売りはじめました。このお菓子は保存がきいたおかげで、巡礼者がそのお菓子を家族に持ち帰り、各地に伝わることになりました。
修道院には蜂蜜パンをつくり、それらを広めるための条件がそろっていました。さらに、修道士は昔から食いしん坊で、おいしい食べものを追求するのが得意でした。
蜂蜜パンにスパイスを加える
中国でつくられていた、もしくはヨーロッパでつくられていた蜂蜜パンに香辛料が加わるのはいつなのかははっきりとしていません。
7世紀、修道院では香辛料入りのパンが作られていたという記録が残っています。その後8世紀に入るとパリで行商によりパンデピスが売られていました。ただ、パリでパンデピスは定着せず、ほかのフランス地方で特産になっていきました。
1705年に発行された辞書(le dictionnaire de Trévoux)には『灰汁と蜂蜜とスパイスを加えたパン』と記されています。灰汁とは砂糖工場で砂糖を取り出す際に出る汁のこと。
17世紀後半にはすでに香辛料を加えたスパイスパンがあったことが分かります。さらに、ランス(Reims)とヴェルダン(Verdun)のパンデピスが最もおいしいと評価されていました。
1452年、フィリップ3世はベルギーの町コルトレイク(仏クートレ Courtrai)でミツバチの砂糖(蜂蜜)のガレットに出会い、そのおいしさに感動しました。彼は職人を連れて帰り、ディジョンにて蜂蜜のガレットをつくらせました。
フィリップ3世(Philippe III, 1396年7月31日 – 1467年6月15日)は、ヴァロワ=ブルゴーニュ家の第3代ブルゴーニュ公(在位:1419年 – 1467年)。「善良公」(le Bon ル・ボン)と呼ばれています。
これをきっかけにディジョンの町中でもパンデピスが広まっていきました。
ただ、このときは蜂蜜パンという記録しか残っていません。ブルゴーニュ地方でパンデピスの記述は18世紀に入ってからです。
1702年の陳情書で、ディジョンのパティシエ菓子職人の親方が「町と隣村の住民が菓子やタルト、パンデピスなどを道や町の入口で売っている!」と苦情を訴えたものでした。
おいしい知識を手に入れよう!お菓子のレシピから学ぶフランス語講座
フランスのお菓子は世界的に有名ですが、なぜそのおいしさに魅了されるのでしょうか?
「お菓子のレシピから学ぶフランス語講座」では、フランスのお菓子作りの秘訣を探りながら、同時にフランス語を学んでいきます。
この講座では本場フランスのお菓子のレシピをフランス語で読み解きながら、フランス語を習得します。マドレーヌ、タルト、シュークリームなど、フランスでも定番のお菓子のレシピを通じて、フランス語の基礎から応用まで幅広く学ぶことができます。
フランス語の勉強が初めてでも大丈夫です!当講座では基本的なフランス語表現から、食材や道具の名前、作り方までを丁寧に解説しています。おいしいお菓子のレシピを作りながら、楽しくフランス語をマスターすることができます。
フランス語を学ぶだけでなく、お菓子作りの知識も身につけることができるこの講座は、フランス語学習者とスイーツ好きな方にとって理想的な組み合わせだと思います。ご自宅で学べるダウンロード形式なので、時間や場所に制約されずに勉強することができます。
「お菓子のレシピから学ぶフランス語講座」に参加して、おいしい知識を手に入れましょう!フランス語の魅力とフランスのお菓子作りの楽しさを同時に体験し、自分自身を豊かにしませんか?ご参加をお待ちしています!
関連記事